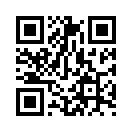2017年03月03日
三月三日は雛祭り。

今朝は幾分寒さが和らいだ気がしましたが、まだまだ寒い朝です。
小学校は未だですが、高校生の卒業式が行われました。
この時期になりますと若い頃の東京の大学に行くときの
わくわくしたような気持ちが思い出されます。
どなたも青春時代の高揚した気持ちを思い出しませんか・・・。
さて、我が家でも床の間にお雛さんを飾りました。
気持ちの切り替えと季節感を感じます。
ひなとは小さくかわいい物を言いますが、それにしても女衆は
飾りつけをし、またすぐ仕舞い来年まで忙しいことです。
雛祭りが終わってすぐかたずけないと「お嫁に行くのが遅くなる、
あるいは行けなくなる」などの風習があります。
これはもともと「雛流し」の風習の名残りで紙でできた人形の雛で
けがれを流すことでしたが、ひな人形が立派になり流さなくなりました。
けがれを流した雛は早くしまいましたが、この時期は春の植え時で
農作業も忙しくなるころですのでそんな言い伝えになったようです。
Posted by いそさん at
07:19
Comments(0)
2016年09月10日
伊豆下田の写真コンテストは10・31までです。

おはよう、今朝の涼しさは久しぶりでした、朝焼けでしたので雨が近いでしょう。
下田の温泉ホテルいそかぜのいそさんです。
下田が生んだ商業写真の開祖「下岡蓮杖」は下田開港の時、居留人から
写真術を伝授され、横浜で開業しましたが名前は出身地から
下田、岡方村の桜田性でしたが、下と岡を取り号の蓮杖を付けたものです。
そこで、商工会議所(0558-22-1181)が中心となり
町おこしの一環として下岡蓮杖写真コンテストを実施しております。
応募料は無料です。
部門はランドスケープの部(風景写真)環境ポートレートの部(人と景観)
組み写真の部(3枚1組)の3部門です。
写真は下田公園にある碑と胸像です。
私は須崎の爪木崎の風景は日本一だと思っています。
勿論夏や冬の水仙の風景も素晴らしいですが、青い海と白い灯台
遠く伊豆七島、岬を行きかう船の数々一日中見ていても飽きません。
そんな爪木崎や遊歩道の朝日や夕日是非、どなたか撮ってください。
かってなおねがいですが、応募して頂くとありがたいです。
詳細は上記にお電話お願いします。
Posted by いそさん at
06:50
Comments(0)
2016年09月07日
菊の節句、重陽の節句が近ずきます。

おはよう、下田の温泉ホテルいそかぜのいそさんです。
13号が発生で進行方向が心配になります。
さて、各地では菊の花の展覧会がも要される季節になりました。
きのうはカマスの大漁をお知らせしましたが、旬の魚はシマアジだそうです。
名前の由来は伊豆の島々で取れるので島アジの名前がついたそうです。
私はなんと言っても目黒の秋刀魚ではないですがサンマの丸焼きに秋を感じます。
旬の花は秋の七草ですが黄色の女郎花が好きです、また、ススキも
秋ですが爪木崎には西洋ススキが見事に咲いています。
夏から秋にはチチンと呼ぶ小鳥鶺鴒が地面を這うように飛びます。
これも秋の鳥です、以前には黄色のセキレイもいましたが今は見かけません。
アワビの旬も秋だそうです、夏とばかり思っていました。
秋と言えば嫁に食わすなと言われる秋ナスも旬です。
焼き茄子を冷やしてオカカをかけて飲む晩酌は最高です。
写真は青い温州ミカンです、もうすぐ赤らむでしょう。
本日は茨木の友人からナシが届きました季節の果物です。
今朝の下田の空は秋の鰯雲が広がっています、この後台風が
来ないとよいですが、足元を見ますとオシロイバナが白や赤の花をつけて満開です。
Posted by いそさん at
06:58
Comments(0)
2016年08月15日
田舎の盆行事の教え。

皆さんおはようございます、下田の温泉ホテルいそかぜのいそさんです。
昨日は強い日差しのない一日でしたので、その分涼しい日でした。
お盆で日本の民族大移動と言われる日ですので、
道も混み海水浴場もパニック状態でした。
かててくわえて、下田まつりで交通規制ですし、そのうえ6日には皇太子ご夫妻も
須崎御用邸でご静養されます。
また、私はお寺の檀家総代ですので一日中、盆の施餓鬼の立ち合いです。
このお盆の時期がこの夏のピークでとにかく忙しいです。
肝心のお盆のことですが、ご先祖様が自宅の仏壇に帰ってくる日です。
仏壇には初物の粟やサツマイモ、サトイモ、ホオズキ、などを飾ります。
お盆の入りは迎え火は早い時間に焚き、先祖に早く来てもらい
送り火は遅くまでいてもらうため、遅く炊きます。
ナスやキュウリの馬も胡瓜の馬で早く来てもらい、茄子の牛でゆっくり変えると
謂われます、昔の人のこじつけでしょうが先祖を思う気持ちが伝わります。
そのほか子供のころはよく見ましたが、海施餓鬼と言って海岸に
蓆を広げお年寄りのおばあさんたちがカネをたたき念仏を挙げていました。
理由を聞くことがありましたが、海で死んだ人の霊やアワビやさざえの霊に
感謝の念物だと言われました。
今は念仏を申す人もなくなり、坊さんの檀家回りも簡素化されました。
これからますます世知辛い世の中になります。
昔の伝統も残したいと思うこの頃です。
Posted by いそさん at
06:37
Comments(0)
2015年10月13日
鯉名の銀平と初代式守伊之助の出身地。

秋になり朝夕の陽が綺麗に映える季節になりました。
伊豆白浜の海岸から伊豆七島の利島を臨み雲間から昇る日の出です。
肌寒くなりましたがサーファーは夜明けにもやっていました。
さて、昨日の続きですが相撲の技の河津掛けを紹介しました。
相撲の行司の初代、式守伊之助は南伊豆町弓ヶ浜近くの手石地区
(昔は鯉名と呼んだ)出身で初代は江戸時代の人です。
また、三波春夫の歌、雪の渡り鳥の主人公(鯉名の銀平)も
同じ地区の出身です。
江戸時代は旅は歩きでしたので、帆船は今の新幹線と同じでした。
帆船時代は下田は風待ち港として殷賑を極めました。
今日でも新幹線駅は人が集まる都会地となっていますので下田からは
行司や、やくざだけでなく写真の開祖や文学者も輩出しています。
最近の相撲界では呼び出しの秀男は引退しましたが、白浜の出身で
高校の後輩でもあります。
Posted by いそさん at
07:56
Comments(0)
2015年05月07日
韮山反射炉、世界遺産になるか・・・。

イコモスの勧告が韮山反射炉にありました。
写真は了仙寺の下田和親条約が調印された境内のジャスミンの花です。
実はこの反射炉はこの寺と深い関係があります。
反射炉の準備も出来資材も揃い下田で建設される予定でしたが
ぺりーが来たことで急遽中止になり資材も韮山に運び建設されたものです。
幕府は製鉄技術などアメリカに見せたくなかったのでしょう。
また一方ではっぺりー艦隊を追いかけ吉田松陰、金子重輔主従も来ました。
伊豆の代官江川太郎左衛門は須崎のスサリにお台場を建設
韮山で作った大筒を5台付けペリー艦隊に備えました。
その後江戸海防のため現在の東京お台場にこの大砲も移動しました。
現在も須崎ではお台場の地名は残り小さな石碑を置いてあります。
須崎区有古文書にはその時の配置図等の絵図面も保存してあります。
またぞろ訥国からいちゃもんがついたようですが、時の代官
江川太郎左衛門の句「里はまだ夜更かし富士は朝日陰」
心意気が伝わります。
Posted by いそさん at
07:40
Comments(0)
2015年05月05日
こどもの日。

皐月の空に吹流しーー5月の鯉のぼりは腹を風が吹き通し
腹には一物持たない縁起物ですがこの頃は鯉のぼりは立てません。
昔はあの家の何番目の子供と分かりコミニュケーションが取れました。
田舎の須崎では今朝も菖蒲を屋根に上げる風習が残っております。
以前はどの家もやっていましたが今は少なくなりました。
朝国旗を上げているとき近所の人が(アルケー)と言って頂きましたので
我が家も屋根に上げました。
写真は黒船祭のパレードに参加した海上自衛隊の音楽隊です。
黒船もこのあと5月15日から始まります。
安倍総理の訪米には米大使もアメリカにいましたが
下田には帰れるでしょうか、まだ発表はありません。
Posted by いそさん at
09:03
Comments(0)
2010年05月15日
黒船祭りパート3(歴史こぼれ話)
写真は黒船祭りに沸く町内の通りでのイベントです。
下田の温泉旅館、海辺のお宿「ホテルいそかぜ」のいそさんです。
普段は人通りの少ない町中もご覧の通りの人出になります。
黒船祭りのメインの記念式典や海兵隊のカラーガードを先頭に自衛隊
警察隊、小学生の鼓笛隊などが続きます。
下田市長とアメリカ大使が乗ったオープンカーのパレードも名物になっています。
歴史の本には出てきませんが、嘉永七年152年前、艦隊乗組員は
柿崎の浜辺に上陸しピクニックをしました。
付近の住人は雨戸を閉めその様子を見ていました、彼らは赤ワインを飲みました。
それを見た人々はアメリカ人は、人の血を飲むと恐れたと古老の
昔話に聞きました、開国の始めにはいろんな事があったのでしょう。
しかし、下田では欠乏所を作り日本で最初の市民レベルの交換所ができ
外国人との交流は下田の町から始まりました。
下田での市民レベルの交流から長崎・函館でも許可が出ました。
下田が市民外交の発祥の地とも言われます。
Posted by いそさん at
18:20
Comments(0)
2010年02月03日
須崎の節分絵の豆まき。
あしたは、立春もう春ですねえ、今日は豆まきの日です。
下田の温泉旅館、海辺のお宿「ホテルいそかぜ」のいそさんです。
私の子供の頃は手ぬぐいで作った袋を持って各家を回って豆を撒いてもらい貰いました。
炒りたての熱い豆が首筋に入り泣いたのを懐かしく思い出します。
さて、近頃の豆まきは少子化や最近の家は広い部屋が無い為集会場に子供を集めます。
写真は豆まきの前にお話をしている所です。
昔の豆まきは大豆だけでしたが、この頃はみかんやお菓子のほうが多いいようです。
須崎ではこどもの行事として1月「どんどん焼き」2月「節分の豆まき」
8月「お盆行事」などまだ生きています。
伝統は地域に残して生きたいと思います。
Posted by いそさん at
20:00
Comments(2)
2009年02月04日
テンちゃん便り(節分行事の今昔)
みなさん、おはよう。ぼくテンちゃん昨日は豆まきです。
写真の中央はお母さんです、昔は各家庭で豆まきをしていました。
お母さんは女性の会の会長ですので、集会所に子供たちも集め各家庭の豆まきは
止めにしました。
昔は小学生は袋を持って各家を回って豆撒きに言ったものです。
とうちゃんの子供の頃は炒りたての熱い豆を撒いてくれました。
熱い豆が首筋に入ったりして痛かったのを覚えています。
時代は変わって昔は豆ばかりで少し「こうじみかん」が入るぐらいでした。
今の時代は豆よりもお菓子の袋のほうが多いいです、時代は変わりましたねえ。
節分は年、四回あります立春、立夏、立秋、立冬ですが、
今は二月の節分が豆まきで有名になりました。
二月の節分は立春の前で旧暦では年の暮れで豆を撒き一年の邪気を祓ったものです。
節分はまさに季節を分ける行事で立春を向かえ今日からは正月、初春を迎えます。
隣のおじいさんの大きな声で「福は内、鬼は外」耳の底で聞こえます。
いよいよ、本格的な春です、河津桜も色ずきました。 お出かけ下さい。
Posted by いそさん at
09:53
Comments(0)
2008年09月23日
秋分の日(お彼岸の中日)。
みなさん、おはようございます。
下田の温泉旅館「海辺のお宿いそかぜ」のいそさんです。
写真は秋の海になったホテルの前の太平洋です。
遠くに利島と新島が望見されます、海ではワラサやワカシが釣れて釣り船も大忙しです。
きょうは、お彼岸の中日私の日記を見ると5年間晴れが続いています。
きょうは、昼と夜の時間が同じ日でこれからは夜が長くなつて来ます。
読書の季節と言われる所以でしょう。
又きょうは、太陽は真東から昇り真西に沈む日でもあります。
写真の利島の左、丁度写真の切れる辺りが東です、西は対岸の田牛海岸の後ろに沈みます。
お正月には石廊崎の先端の海に沈みます、感動的です。
お彼岸は西に沈む彼方の西方浄土、ご先祖の死者の世界をお祈りするものです。
ご先祖を静かにしのぶ一日にしたいと思います。
Posted by いそさん at
08:19
Comments(0)
2008年09月22日
テンちゃん便り(暑さ寒さも彼岸まで)。
みなさん、こんにちは。
ぼくは、下田の温泉旅館「海辺のお宿いそかぜ」アイドルワンちゃんテンです。
台風一過の後本当は晴れるのに、きのうは雨でした。
おかしい天気ですねえ。
ぼくの自宅の座敷の写真です、我が家は10月になると縁側の障子をはめます。
なにしろ我が家は江戸時代の元治元年の建築ですから暑い時期は障子を全部取り払います。
時代は幕末で池田屋の変があったときの造りですので、夏は涼しいですが冬は寒い家です。
恒例の行事として我が家の当主のお仕事です、とーちゃんは春に障子をはづし秋にはいれます。
昔の人は、よくいつた者ですね。
暑さ寒さも彼岸までと、本当に寒くなるから不思議ですねえ。
みなさんも、お風邪など召しませんようにお気をつけ下さい。
Posted by いそさん at
13:00
Comments(0)
2008年08月15日
テンちゃん便り(須崎のお盆の風習)
みなさん、おはよう。ぼく下田の温泉旅館「海辺のお宿いそかぜ」のテンです。
写真は、ぼくの家のお仏壇です、ナスの牛とキュウリの馬がいます。
頭の上には盆の飾りつけがいっぱいです。
迎え火を焚いて、ご先祖が道に迷はない様に目印とし、お墓からキュウリのお馬で早く帰り
送り火を焚いてナスの牛に乗ってゆっくりお帰りになると聞いています。
それから、須崎ではお盆と祭りは村休みと言って海にも畑にも行ってはいけない。
この風習は江戸時代から続いています。
もう一つこのお盆の時は子供は潮あび(海水浴のこと)をしてはいけない。
このことは、大人が海に出ていないので未然に事故を防ぐ昔の人の知恵でしょう。
このほかには、ヘビを海に捨てると大きな台風(シケ)が来ると言ったものでした。
昔からの風習も今は大分廃れてきました。
Posted by いそさん at
08:11
Comments(0)
2008年08月14日
テンちゃん便り(迎え火と常務初登場)
みなさん、おはよう。ぼく下田の温泉旅館「海辺のお宿いそかぜ」のテンです。
夕べは門外で迎え火を焚きました。
写真はまだ火をつけたばかりで煙いです。
写っているおにいさんは、とーちゃんの弟の常務です。
お盆の迎え火は家族が揃ってご先祖をお迎えします、田舎は盆の行事として残っています。
Posted by いそさん at
07:58
Comments(0)
2008年08月13日
テンちゃん便り(須崎の旧盆)
みなさん、おはよう。ぼく下田の温泉旅館「海辺のお宿いそかぜ」のテンです。
きょうも暑くなりそうですね、だけど朝のうちは涼しいですよ。
須崎は今日から旧盆です、お母さんは墓参りや仏壇の飾りつけ、なす馬等作って大忙しです。
盆休みでホテルは忙しいですが、季節は立秋を過ぎましたので朝晩は秋風が感じるようになると思います。
夕方にはお盆の行事の迎え火を焚いてご先祖様をお迎えします。
須崎は田舎ですのでどのうちも火をもします、盆の日の風物詩です。
ぼくの立っている門のところで午後4時ごろ迎え火を焚いてご先祖様を迎えます。
Posted by いそさん at
07:41
Comments(0)
2008年06月16日
須崎の朝市

みなさん、こんにちは。下田の温泉旅館「海辺のお宿いそかぜ」のいそさんです。
須崎は半農半漁の集落です、昔と違って今はサラリーマンが増えました。
しかし、お年寄りが長生きの村です、特に畑仕事はお年寄りの仕事です。
静岡県でも地産地消、運動が盛んです。
県から補助をいただき、テントを作り朝市会場を作りました。
この元気なお年寄りに朝の取立て野菜を売ってもらいますが、日曜日の七時からですが直ぐ売り切れになります。須崎は急斜面にへばりつくように家が建っています。
この坂を歩いている聖か、長寿村です。
テンちゃんのお散歩コース沿いにあります。
Posted by いそさん at
18:15
Comments(2)
2008年05月09日
須崎地区の昔からのしきたり。
みなさん、こんにちは。下田の温泉旅館「海辺のお宿いそかぜ」のいそさんです。
昨日貝類(あわび、さざえ、とこぶし、うに)の口開け(解禁日)でした。
朝、5時頃地区の漁協関係の役員が集まり、口開けをするか協議します。
口開けが決定すると各組ごとに、「ふれつぎ」と言って一番はずれの家から貝の口が開いたこと
時間は9時から、箱メガネで取ること、水に潜ってはいけない、等を午前6時頃「ふれつぎ」と
言い順番に申し送ります、
この方法は江戸時代から続く伝達の仕方です。
こんなことで、村のコミュ二ケーションが出来ているのかもしれません。
写真はライブカメラから見たホテル前の海です。
Posted by いそさん at
18:15
Comments(2)
2008年04月03日
恵比寿島の日時計。
みなさん、こにちは。下田の温泉旅館「海辺のお宿いそかぜ」のいそさんです
写真は恵比寿島の日時計、石廊崎を向いた先端に位置しています。
日時計などどこに設置しても同じかと思っていましたが、どうも難しいらしくいろいろ調査して
下田市の教育委員会が作りましたので正確なものです。
夏の日暮れが長いとき、犬の散歩のときなど時間を見るとき便利です。
秋の日はつるべ落とし、夕方のすんだ空がきれいに晴れ渡ります。
冬の日は真っ赤な太陽が石廊崎の海に沈みます感激の一瞬です。
Posted by いそさん at
16:15
Comments(0)
2008年02月26日
手作り、雛人形。
フロントに飾りました、お客様から可愛いね・・と言われます。
当館の大女将、92歳がボケ防止に紙人形を作っています。
いろいろありますが、最新の作品は雛人形です、その他踊り子人形、唐人お吉、歌舞伎人形。
五月人形、旅がらす、七夕人形、藤娘、大正ロマン、サンタクロースなど。
小物では、楊子入れ、ティッシュ入れ、ボールペン差しなど。
風の花車では、水仙風車、紫陽花、さくら草、矢車草、チューリュプなど造っています。
数に限りがありますが、プレゼントしていますので、おもうしつけ下さい、品切れのときはご容赦下さい。
Posted by いそさん at
18:30
Comments(2)





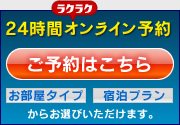
 ホームページはこちらから
ホームページはこちらから 今の須崎の様子は?
今の須崎の様子は? 下田のお天気はこちらから
下田のお天気はこちらから